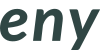レンガ鏝とはレンガ積みに使われる金ごての一種で、ブロック積み・レンガ積みの職人から愛用されている左官道具の一つです。日本では兵庫県三木市で多く生産されていて、ナルセ商工や五百蔵製作所など鏝・金物専門メーカーの製品が人気を集めています。
レンガ鏝のラインナップを見ていくと、コテ面にはさまざまな形状があることに気付くでしょう。桃型・お福型のように見た目がとても似ているものから、円形・ひし形など特殊な形状もあります。レンガ鏝の選び方には形状・サイズのほかにどのようなポイントがあるのでしょうか。レンガ積みでの使い方からおすすめ商品までをご紹介します。
レンガ鏝の用途

出典:amazon.co.jp
レンガ鏝はモルタルを攪拌する・すくう・塗る・ならす用途に使われます。明治期には柳刃鏝でレンガ積みがされていましたが、外国から輸入されたレンガ鏝の形状が採り入れられ、現在の形にまで発展してきました。
レンガ、と名前についていることからレンガ積み専用と思われるかもしれません。しかし小さく幅広な面を持ったレンガ鏝はモルタルに関わるさまざまな作業に使いやすく、実際にはブロック積み・タイル貼りにも使われます。
レンガ鏝のコテ面は丸みを帯びていて、サイズは手のひらほどか、それより少し大きいくらいしかありません。先端と縁を使うことでレンガにモルタルを盛りつけやすい形状です。土台に重ねたら柄頭でレンガを叩いて水平にし、はみ出たモルタルを剥がし取ります。熟達すれば1本でレンガ積みをスムーズにこなせるようになる道具です。
ブロック鏝との違い

出典:amazon.co.jp
ブロック鏝は細長い台形に似たコテ面を持っています。名前通りにコンクリートブロックの長辺に見合った形状で、モルタルをブロック縁に置いていく、穴に流し込むといった用途に便利です。
長大なコテ面のために扱いは難しく、不慣れだとモルタルをこぼす失敗をしてしまいます。また、ブロック積み以外の作業で使われることはあまりありません。レンガ鏝に比べて専門性をより高めた道具だと言えるでしょう。
レンガ鏝の選び方
レンガ鏝を選ぶポイントは形状・大きさ・柄の3つです。手になじむレンガ鏝は人によって違うものなので、どれが正解と言いきれるものではありません。レンガ鏝でどのような作業をするのか、モルタルを入れている容器はバケツとプラ舟のどちらかなども考えて選びましょう。
形状から選ぶ
レンガ鏝の形状は桃型・お福型の2つが最も多く、その他に円型と特殊型のコテ面が見られます。形の違いで使い勝手も少しずつ異なるため、それぞれの特徴をご紹介していきます。
ブロック積みにも使いやすい桃型

出典:amazon.co.jp
桃型はコテ面にふっくらとした横幅があり、先端に向けてすぼまっています。上から見たときにちょうど桃の実に似た形状で、塗ったモルタルをならしやすく、全形など大きめのレンガに向いています。
縦に長さがあるため、コンクリートブロックの縁に沿ってモルタルを細く置いていくのにも使えるでしょう。桃型は関東で使われることが多いといわれ、廉価なレンガ鏝では多数を占める形状となっています。
モルタルの盛り付けに適したお福型

出典:amazon.co.jp
お福型またはおたふく型は、形状が桃型と似ています。桃型と比べると膨らみが下側にきているのが特徴で、下ぶくれのお福面に似ていることから名付けられたのでしょう。主に関西で使われているタイプです。
モルタルをすくったときに大きな塊にしやすく、小型レンガの表面に盛り付けやすい形状です。ブロック積みに使えないことはないものの、縁沿いでは素早く引かないとモルタルがあふれてしまいます。
塗り作業に便利な特殊型

出典:amazon.co.jp
ひし形に近いコテ面を持つレンガ鏝は、メーカーによってはA型やB型とも呼ばれ、柳刃鏝に近い形状です。細身のコテ面はモルタルを壁面に塗りやすく、小型レンガを積む際やタイル貼りに便利なタイプです。また、ブロックへのモルタル流し込みにも重宝します。
バケツ底のモルタルまですくいとれる丸型

出典:amazon.co.jp
丸型のコテ面を持っているので、バケツの底に残ったモルタルもしっかりすくって取れます。桃型・お福型のように先端がとがっていないので容器を傷つけることがなく、長さのないコテ面がバケツ底にまでしっかり届きます。
この1本で盛りつけからならしまでこなすのは難しいので、桃型などのサブ鏝として持っておくと良いでしょう。しかし、底面が四角いプラ舟には向きません。
レンガの大きさに合わせて選ぶ

出典:amazon.co.jp
レンガ鏝は1番から5番までのサイズがあり、1番がもっとも大きく、5番に向かうほど小さくなります。大型のレンガであれば置くべきモルタルの量も増えますから、レンガのサイズにあわせてレンガ鏝も使い分けてください。
小型のレンガであれば4・5番、全形レンガなら2・3番を使うとよいでしょう。1番はブロックや大型のレンガを積むのに向いたサイズです。ただし、1番ほども大きい面を持つ鏝はバケツに入りませんので、モルタルを練るのはトロ箱のように平たい容器にしましょう。
容器に合わせて柄を選ぶ
レンガ鏝を選ぶときにコテ面の形状にばかり目が行っていませんか。手で握る柄の部分も用途によって向き・不向きがあります。ここでは柄の角度に着目して、プラ舟用・バケツ用に分類しました。
トロ箱や鏝板で扱いやすいプラ舟用

出典:amazon.co.jp
柄の角度が控えめで、プラ舟の縁にかけやすい造りです。腕の角度とコテ面に角度差が小さく、高い場所へも安定して持ち上げられます。また、コテ板にモルタルを乗せてレンガ鏝ですくっていく用途でも使いやすくなっています。
高いレンガ壁を作る場合、プラ舟用の柄ならすくったモルタルを自然な手のはこびで持ち上げて、レンガの上へと置いていけるでしょう。一方、バケツに使おうとすると容器内で柄がつっかえてコテ面が斜めになってしまい、うまくモルタルをすくい取れません。
バケツから直接取るのに適したバケツ用

出典:amazon.co.jp
バケツ用の持ち手は、プラ舟用に比べて上へと向いています。深く狭いバケツ容器の中でも面を水平に保てるためモルタルがすくいやすいタイプです。残り少なくなったバケツ底のモルタルもしっかり取れます。
バケツ用の柄はサイズの小さな鏝に向いています。小型レンガを積んでいく用途なら、コテ面が小さくバケツからすくい取りやすいバケツ用がおすすめです。ただし持ち手が上向きなので胸より上に安定して持ち上げるのは難しく、鏝板にモルタルを乗せて塗っていく、という用途には向きません。
レンガ鏝のおすすめ人気ランキング10選
レンガ鏝の中でも人気の高い商品を10個ピックアップしました。コテ面の形状・サイズ・使用素材など、どの製品にも特色があります。とくに左官職として働いている方は、職人用・左官用と明記された商品から選ぶことをおすすめします。
1位 児玉製作所 ヤマ六 レンガ鏝 NO.2

amazon.co.jp
サイズ:140 × 155 mm(コテ面)
重量:277g
DIY用の大きめなレンガ鏝
2番サイズで、全形レンガにモルタルを盛る用途に使いやすい大きさです。柄の角度が低いためプラ舟とセットで使いましょう。DIY向けですので、仕事で使うには耐久性に不安が残ります。
2位 スーパーレンガ鏝 (薄手) No.4 カネミツ

amazon.co.jp
サイズ:130 × 145 × 275mm
重量:250g
ならし作業がしやすい薄手仕様
モルタル表面をならしやすい薄手づくりの鏝です。4番のお福型なので小型レンガにモルタルを盛るのに便利でしょう。柄はあまり上向きではないため、プラ舟か鏝板と合わせて使うことをおすすめします。
3位 ナルセ商工 カネ三 本焼レンガ鏝 REKN04

amazon.co.jp
サイズ:135 × 145 mm(コテ面)
重量:270g
特殊鋼に焼き入れを施した高耐久鏝
特殊鋼を焼き入れ後に焼き戻し、研磨にて仕上がっています。モルタル塗り使っても傷みにくく、きちんと手入れすれば長く使えるでしょう。柄は上向きなのでバケツにも入れやすくなっています。
4位 五百蔵製作所 カネ千代 ニュー本焼 レンガ鏝 薄手 #1

rakuten.co.jp
サイズ:155 × 176 mm(コテ面)
職人向けの高品質なレンガ鏝
職人用鏝を中心に製作している、五百蔵製作所の大型レンガ鏝です。本焼きがされたコテ面は耐久性があり、薄手仕様なのでモルタルならしがしやすくなっています。柄はプラ舟に向いた角度なのでその点は注意してください。
5位 五百蔵製作所 カネ千代 レンガ鏝 薄手 #6

rakuten.co.jp
サイズ:125 × 110 mm(コテ面)
小型サイズにより繊細な作業がしやすい
こちらも五百蔵製作所のレンガ鏝で、5番よりもさらに小さい6番サイズを採用しました。コテ面はやはり本焼きされた薄手仕様となっています。小型なのでバケツ内でも取り回しが簡単です。
6位 藤原産業 赤長 ステンレスレンガ鏝 NO.5

amazon.co.jp
サイズ:110 × 80 × 260 mm
重量:187g
小型レンガを扱う作業に最適なサイズ
多彩な工具類を販売している藤原産業が送る、安価なレンガ鏝です。小型レンガを積むのに便利な5番サイズを採用しているので、庭にちょっとレンガの花壇を作りたい時に便利でしょう。コテ面にはステンレスを使用し、錆に強い商品です。
7位 嘉彦 レンガコテ (大) #1

amazon.co.jp
サイズ:150 × 165 mm (コテ面)
重量:286g
DIYでレンガを使う方におすすめ
とても安価な1番サイズのコテです。庭づくりやDIY作業で大型レンガを積みたいときには十分使えるでしょう。サイズからするとプラ舟や鏝板向きです。コテ面に使っている金属が錆びやすいため、使用後の手入れや保管には気を遣う必要があります。
8位 藤原産業 金長 レンガ鏝 薄手 #2

amazon.co.jp
サイズ:150 × 340 × 110 mm / 150 × 170 mm(コテ面)
重量:261g
耐久性が高いコテ面を持つ薄手レンガ鏝
藤原産業の鏝ブランドの中でも、金長はやや高めのラインナップです。サイズは全形レンガに使いやすい2番を採用しました。コテ面素材には炭素鋼を使用して耐久性を高め、モルタルのすくい・ならしがしやすい薄手仕様です。柄にはそこそこ角度があるため、バケツに入れても使えるでしょう。
9位 カクマン(普及型) 並 バケツ鏝

amazon.co.jp
バケツからのモルタルすくいに便利な丸型
バケツ底のモルタルを最後まですくいとれる丸型のレンガ鏝です。コテ面の素材は錆に強いステンレスを使用しています。DIYが趣味の人だけでなく、プロの職人でも持っておくと重宝するのではないでしょうか。
10位 藤原産業 赤長 ステンレスレンガ鏝 バケツ用 丸型

amazon.co.jp
サイズ:117 × 143 × 288 mm
重量:260g
直径30cm程度のバケツでも底まで届くサイズ
こちらもステンレスを使用した丸型です。柄まで含めても全長30cm以下なので、直径のやや小さいバケツでも最後まですくい取れます。サイズが明記されているので、お手持ちのバケツと大きさが合うか不安な方はこちらを検討してみてください。
おすすめの商品一覧
| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |
|---|---|---|---|

児玉製作所 ヤマ六 レンガ鏝 NO.2
1
|
1,827円 |
     4 |
  |

スーパーレンガ鏝 (薄手) No.4 ……
2
|
2,257円 |
|
   |

ナルセ商工 カネ三 本焼レンガ鏝 R……
3
|
1,760円 |
|
    |

五百蔵製作所 カネ千代 ニュー本焼……
4
|
3,120円 |
|
  |

五百蔵製作所 カネ千代 レンガ鏝 ……
5
|
3,120円 |
|
  |

藤原産業 赤長 ステンレスレンガ鏝……
6
|
725円 |
|
    |

嘉彦 レンガコテ (大) #1
7
|
452円 |
    
|
    |

藤原産業 金長 レンガ鏝 薄手 #2
8
|
3,817円 |
|
    |

カクマン(普及型) 並 バケツ鏝
9
|
945円 |
    
|
   |

藤原産業 赤長 ステンレスレンガ鏝……
10
|
799円 |
     3 |
   |
使用後はきちんと手入れをする

出典:amazon.co.jp
レンガ鏝のコテ面は金属でできているため、水分を含んでいるモルタルを扱っていく上では手入れが欠かせません。素材にステンレスや焼き入れ鋼を使っている鏝でも放っておくと錆やモルタルが固着するので、使用後には必ずお手入れをしてください。
モルタルを塗り終わった後の鏝は水洗いしましょう。付着したばかりのモルタルなら水洗いするだけで綺麗に落とせます。落ちない部分はブラシで軽くこすってください。洗い終わったら水気をしっかり拭き取り乾燥させます。
モルタルに接着強化剤を混ぜて使っていると、鏝の方にも強化剤がしみ込んでモルタルがこびりつきやすくなります。ブラシがけしても残る汚れは、砥石やサンドペーパーでこすって落とすようにしましょう。しばらく使わない鏝は油を塗って錆び止めしておくことをおすすめします。
まとめ
レンガ鏝はモルタルをすくいとり、レンガ表面に厚く盛ったり、コンクリートブロックの縁に細く置いたりして使われます。手になじむ製品を見つけることは難しいものですが、使いやすい鏝を選べるよう、コテ面の形状やサイズといったポイントをしっかり押さえていきましょう。
大型レンガやブロック積みでは桃型、小型レンガを扱う現場ではお福型・特殊型がおすすめです。丸型はバケツと組み合わせて使うと便利ですが、レンガ表面へモルタルを綺麗に盛るのには向きません。鏝の全長・柄の角度によって適した容器が異なるため、その点も注意して選ぶようにしてください。
それぞれの商品の特徴をおさえ、目的や使用環境に適した商品を見つけてくださいね。