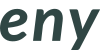検電器とは、電線が活線・充電の状態ではないかを検査するための電気計測器です。配電盤などの修理のために電源を落としたあとに、検電器を使用して停電状態を確かめることで、作業の安全性を確保できます。電気技師にとって必需品といえるでしょう。
検電器のメーカーでは、長谷川電気工業や共立電気計器、日置電機が人気製品を多数展開しています。危険を伴う検電作業にはどのような商品がよいのか、検電器の原理による違いや、電流・電圧に適した選び方をご紹介します。
検電器の使い方

出典:amazon.co.jp
まずは検電器を使う前に、検電器が正常に動作するかをチェックしてください。電池使用の製品ならスイッチを入れて電池が消耗していないかを確認します。その後で安全性の確認ができているコンセントに差し込んで、検電器の検知部が光るかを見ましょう。
検電器のチェックが済んだら、検査対象の導線部に検知部を当てていきます。電気が流れている場合、ランプが光ったり音が鳴ったりすることで活線状態を教えてくれる仕組みです。電気が流れていなければこれらの機構は動作せず、音や光は発生しません。
なお、検電器を使う目的は、電気が流れていないことを確かめるためです。大抵の製品は安全対策がされていますが、それでも活線・充電状態の導線は危険といえます。活線状態と分かっているものに使用するのは避けてください。
検電器の選び方
検電器は、検電をする原理と測定可能な電流・電圧、検査方法に違いがあります。どのような用途に使用するかを考えながら選んでいきましょう。
原理・仕組みから選ぶ
検電器の種類はどのような原理によって動作をするのか、内蔵している仕組みによって4種類が存在します。電気技師の方が使用するのであれば電子式検電器がおすすめです。
研究・教育用のはく検電器

密閉されたガラス容器の蓋を金属棒がつらぬき、容器外に金属板、容器内には2枚の金属箔が入っています。上部の金属板に物体を近づけることで、帯電しているかを調べることが可能です。
静電気などで帯電した物体を近づけると、金属板には帯電体と異種の電荷が発生します。同種の電荷は対極にある2枚の金属箔に集まります。同種の電荷は反発しあい箔が開くことにより、帯電していることが分かる原理になっています。
この箔検電器は高校理科での実験教材など、学生の電気への理解を深めるために使用されます。サイズが大きく精度もよくないため、検電作業に用いることはありません。
電源不要で回転する風車式検電器

風車式検電器は、高電圧設備の活線状態を調べるための器具です。送電鉄塔の絶縁器具であるガラスは、何らかの原因でコロナ放電と呼ばれる放電現象を起こします。この状態のガラス に風車式検電器を近づけると、イオンの動きを感知して内部の車輪が回る仕組みです。
イオンの流れを感知するため電池がいらず、電子パーツ不使用であることから経年劣化の影響も少ないのがメリットです。とくに高い架空電線を安全な場所から検査する都合上、風車の回転で遠くからでも判断できるのはありがたい点でしょう。
コロナ放電は高電圧がかけられている状況で発生するので、放電が発生しない低電圧域では風車式検電器は適しません。全長も1m以上がほとんどなので、小さな配電盤の検電に使用するには大きすぎます。
電源不要で発光するネオン式検電器

出典:amazon.co.jp
ネオン式検電器は主にペン型で、内部にネオン管を内蔵しています。わずかな電流でもグロー放電により発光するネオン管の特性を活かし、低圧用から高圧用まで広く使われているタイプです。
電流がネオン管を通れば発光するため、電池は不要です。しかし、明るいところではネオン発光の判別がしにくく、絶縁被覆の上から検電することもできません。現在では検電ドライバーに使われることが多く、検電器としての人気は低くなっています。
付属機能が多い電子式検電器

出典:amazon.co.jp
電子式検電器もペン型が多いタイプで、内部には電子増幅回路が組み込まれています。弱い電流を感知すると回路が増幅し、LEDライトの点灯・アラーム音の発生などを起こす仕組みです。
増幅回路を働かせるために電池は必要ですが、この増幅回路をどのように設計するかにより多彩な機能を持たせられます。高圧・低圧兼用にすることもできるほか、絶縁被覆の上からでも検電することができます。
なお、電池を使用するため電池切れの可能性はいつでも考えなければいけません。ほとんどの電子式検電器には電池電圧のチェック機能がついているため、使用前に電池消耗を確認しましょう。
電流の種類から選ぶ
電流は交流・直流の2種類があります。コンセントや一般的な送電線・配電盤であれば交流、バッテリー駆動のものは直流です。
検電作業で使うことが多い交流用

出典:amazon.co.jp
送電線では交流電流が通っており、検電の多くは交流を扱う作業です。そのため、交流用検電器の数は非常に多く見られます。電気技師として働く方なら1本は持っているでしょう。
なお、交流用検電器で直流を検電しても正常に動作しません。感電事故を引き起こす可能性があるため、交流の電線にのみ使用してください。
充電式機器などの検電に使う直流用

出典:amazon.co.jp
電気自動車や一部の電車線のような直流電線に対しては、検電器も直流用を選んでください。直流用検電器はリード線がついており、接地をしながら検電作業を行うことになります。
なお、直流検電では裸線・端子に検知部を接触させる必要があります。感電を防ぐためにも、万全の安全対策をとり使用しましょう。
電圧から選ぶ
検電器の検査範囲は、低圧用・高圧用の2種類があります。低圧用は交流600V・直流750V以下、高圧はそれ以上の電圧に対して使用してください。
家庭内電源の検査に使う低圧用

出典:amazon.co.jp
低圧用の検電器は小型製品が多く、ほとんどはペン型を採用しています。主な用途は家庭用コンセントや配線の停電チェックです。
ペン型の低圧用検電器を選ぶときは、検知部の形状に注意することをおすすめします。コンセント穴に差し込んで使うことが多いため、幅が広すぎないか、長さは足りるかを確認しましょう。
高圧送電線の停電確認に使用する高圧用・特高用

出典:amazon.co.jp
高圧用の検電器は電力設備などの検査に用いられます。持ち手を長く伸ばし、離れたままでも検査できるのが特徴です。検知した時の反応も、強い光や音が発生するなど、離れた場所でも分かりやすくなっています。
高圧用の中には、特別高圧と呼ばれる7000V以上の電圧を検知するのに適した製品もあります。危険な高圧送電線に近づくことなく安全に検査するためには、高圧用・特高用を選びましょう。
検査方法から選ぶ
検電器の検査方法は、検知部を裸線に直接接触させる接触式、絶縁被覆の上からでも検知できる非接触式の2種類です。近年の製品は非接触式が主流ですが、接触式にしかないメリットもあります。
裸線に触れて使う接触式

出典:amazon.co.jp
接触式は、検電器の検知部を直接電線に接触させて計測します。ビニール被覆のような絶縁体越しでは検査ができず、裸線や端子部に当てなくてはいけません。検電方法としては古くからあり、多くの機種が対応している方法です。
検査対象に直接触れるため、正確に調べられるのが接触式のメリットです。半面で活線・充電状態の場合は感電の危険性があるため、検査は慎重に行う必要があります。
被覆の上から検電できる非接触式

出典:amazon.co.jp
非接触式の検電器は感度が高く、電線の絶縁被覆の上からでも電流を検知できます。電気の流れている箇所に触れる必要がないため安全です。静電誘導の電圧から検知するため、蓄電をする直流では使えませんが、交流の検電方法としては広く採用されています。
検査方法は、被覆の上から検電器の検知部側面を当てていきます。検知部の先端を当てるだけでは正確に測定できません。検知部の側面をぴったり当てて、接触面積を増やすのがコツです。
安全かつ便利な非接触式ですが、感度が高いために不要な場所で光ったり、検査対象の停電チェックを正確にできないことがあります。正確な測定のためにも、感度調整ができる製品を選びましょう。
機能から選ぶ
幅広い検電作業に用いられる電子式検電器では、スムーズな検電が行えるようにさまざまな機能が盛り込まれています。
暗所での作業を楽にしてくれるLED照明

出典:amazon.co.jp
検知用ランプとは別にLED照明が付いている製品は、暗い場所での検電作業に便利です。片手で懐中電灯を持つ必要がないため、検電作業に集中できます。
LED照明付きの製品でも、どこが発光するかは製品により異なります。おすすめは先端から照らすタイプです。明るく照らしながら作業できるので、検査対象となる電線を間違えることもありません。
使用前の動作確認を素早く行える電池チェック

出典:amazon.co.jp
電子式検電器であれば、電池残量をチェックできる製品がおすすめです。電池残量がなく、活線状態でも検知できなかった場合は大事故につながりかねません。
検電器を安全に使用するためには、検査前の電池チェックが欠かせません。安価な製品では電池チェック機能がないこともあるため、必ず確認してください。
電池消耗を抑えるオートパワーオフ

出典:amazon.co.jp
多くの検電器は電池を使用する電子式のため、電池の無駄な消耗は避けたいものです。数分間使用しないときには自動で電源を切るオートパワーオフ機能があります。オートパワーオフ機能は電源を切り忘れても、電池消費を最小限に抑えてくれるためおすすめです。
不要な電圧を無視できる感度調整機能

出典:amazon.co.jp
非接触式の検電器では、電圧のかかっている導線が近くにあると勝手に光ってしまうことがあります。誘導電圧を度々拾っていては電池がすぐ消耗してしまいますし、検査対象の活線状態も判別できません。
感度調整とは、検電器の感度を調整することで、拾わなくてもよい電圧を無視する機能です。検査対象の電線に近づけるときだけ感度を上げればよいため、検電作業をスムーズに運ぶことができます。
電子式検電器のおすすめ人気ランキング8選
電子式検電器の人気商品を8個ご紹介します。いずれの製品も高い性能を持っているため、迷ったときには信頼できる有名メーカーから選ぶのもおすすめです。
1位 マーベル ペンライト機能付き検電器 MT81L

amazon.co.jp
重量:30g
測定電流:交流用
測定範囲:AC 40~600V
用途:低圧用
検査方法:非接触式
機能:LED照明・オートパワーオフ・感度調整
暗所でも作業がしやすい
白色のLED照明により、明るく照らしながら作業ができます。検知用LEDは赤色なので、見分けは簡単です。感度調整機能は40~80Vの範囲であり、検査箇所にあわせた感度で検電ができます。
2位 日置電機 3481 検電器
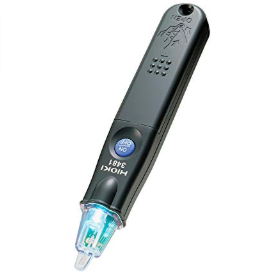
amazon.co.jp
重量:25g
測定電流:交流用
測定範囲:AC 40~600V
用途:低圧用
検査方法:非接触式
機能:LED照明・電池チェック・オートパワーオフ・感度調整
LED照明で暗がりを見やすくできる
さまざまな電気計測器を販売している日置電機のペン型検電器です。必要な機能が全て揃っており、スムーズに作業ができるでしょう。電池残量は先端の緑色LEDが点灯するかどうかでチェックできます。
LED照明は白色で、作業箇所を明るく照らせるようになっています。照明機能のために電池寿命が短くなるものの、停電させている施設の検電作業に適した商品です。
3位 日置電機 3480 検電器

amazon.co.jp
重量:25g
測定電流:交流用
測定範囲:AC 40~600V
用途:低圧用
検査方法:非接触式
機能:電池チェック・オートパワーオフ・感度調整
明るい場所での作業に向いている製品
こちらは上記商品の型番違いで、白色LED照明がついていません。暗所での作業は行わない、ヘッドライトがあるからライトは不要といった方はこちらを選ぶのもよいでしょう。
4位 LOMVUM 検電器

amazon.co.jp
重量:47g
測定電流:交流用
測定範囲:AC 12~1000V ・48~1000V
用途:低圧・高圧兼用
検査方法:非接触式
機能:LED照明・オートパワーオフ
電圧により光・音が切り替わる
比較的安価でありながら、十分な機能を持っている製品です。本体上部にある3つのボタンにより、電源・照明ライト・測定範囲切り替えができます。検知した電圧によりライトの光度とブザーが変わり、危険性を教えてくれる仕組みです。
最低測定電圧は12Vであり、家庭用の低電圧機器の検電にも使えます。最後の操作から5分たつと自動でパワーオフになるため、電池消耗は早くありません。
5位 カスタム 検電器 V-17

amazon.co.jp
重量:24g
測定電流:交流・直流兼用
測定範囲:接触時AC 7~1000V / 非接触時AC 30~1000V / 接触時DC 5~1000V
用途:低圧・高圧兼用
検査方法:非接触式(DC接触式)
機能:LED照明・感度調整
直流・交流を1000Vまで検電できる
測定器を専門に開発しているカスタムの直流・交流兼用検電器です。直流・交流の切り替えは接触・非接触スイッチで行い、どちらも1000Vまでを測定できます。接触式検電であれば100V・200Vの判別ができる表示窓付きです。
6位 Akunsz 検電器

amazon.co.jp
重量:ー
測定電流:交流用
測定範囲:AC 12~1000V
用途:低圧・高圧兼用
検査方法:非接触式
機能:LED照明・オートパワーオフ
信号強度を測定できる
価格が安く、それでいてオートパワーオフやLED照明などの機能を持った非接触式検電器です。交流電流を検出すると赤い光とブザーが鳴り、信号強度によってランプが点灯します。
7位 共立電気計器 低圧用検電器 DX-04

amazon.co.jp
重量:35g
測定電流:交流用
測定範囲:AC 80~600V
用途:低圧用
検査方法:接触・非接触式兼用
機能:ー
電圧の簡易測定もできる検電器
電気計測器の専門メーカーである共立電気計器の低圧用検電器です。検査方法は接触・非接触の2種類を使い分けることができ、手元のスイッチで切り替えます。
充電を検知するとビープ音と4段階のLED光で知らせてくれる仕組みです。LEDは裸線の耐地電圧が55V±15Vから1つ目が発光し、75V±15V・130V±15V・150V±15Vと順に発光していきます。
8位 長谷川電機工業 音響発光式検電器 伸縮式 HSN-6A

amazon.co.jp
重量:227g
測定電流:交流・直流兼用
測定範囲:AC 100~7000V / DC 50~7000V
用途:低圧・高圧兼用
検査方法:非接触式
機能:-:ー
測定範囲の上限が高めの製品
長谷川電気工業は電気計測器の専門メーカーであり、中でも高圧・特高用の検電器を多数生産しています。この製品は低圧・高圧兼用の中でも測定範囲上限が高いのが特徴です。最大810mmまで伸ばせるため、漏電の可能性がある箇所に近づくことなく検電作業ができます。
交流の低圧検電時には銘板部に触れながら検電を行い、高圧検電時には持ち手を握った状態で使用します。直流の検電では必ず付属の接地線をアースに接続してください。
おすすめの商品一覧
| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |
|---|---|---|---|

マーベル ペンライト機能付き検電……
1
|
2,890円 |
     3 |
    |
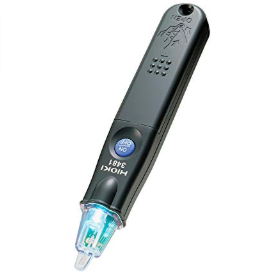
日置電機 3481 検電器
2
|
2,280円 |
    
|
    |

日置電機 3480 検電器
3
|
2,090円 |
    
|
    |

LOMVUM 検電器
4
|
922円 |
|
  |

カスタム 検電器 V-17
5
|
2,461円 |
     4.17 |
    |

Akunsz 検電器
6
|
930円 |
     3 |
 |

共立電気計器 低圧用検電器 DX-04
7
|
3,400円 |
     4.32 |
    |

長谷川電機工業 音響発光式検電器 ……
8
|
29,049円 |
    
|
   |
検電時は絶縁手袋をつけて左手では使わない

出典:amazon.co.jp
検電は電線が活線していないかを調べる作業であり、常に感電の可能性を考えなくてはいけません。そのため、検電器を使用するときには必ず絶縁手袋を着用してください。絶縁手袋が電流の抵抗となることで、感電事故の危険性を抑えてくれます。
また、検電器は右手で持って使いましょう。左手は心臓から近く、絶縁手袋を着用していても安全ではありません。左手が壁などに触れていても、右手から心臓付近を経由して左手へと電流が抜けてしまうため注意してください。
まとめ
検電器は、電線の修理を安全に行うために欠かせない計測器具です。検電器は原理の違いにより4種類があり、一般的な検電には電子式検電器が使用されます。
検電器を選ぶときには、とくに電流と電圧の違いに注意しましょう。電流が直流・交流のどちらであるかにより、選択できる検査方法には差があります。電圧は低圧・高圧の違いだけでなく、測定範囲が対象の電圧に合っているかを確認してください。
検電は正しく行わないと感電事故につながってしまう危険な作業です。正しい検査結果が出せるように、信頼できる検電器を選択しましょう。