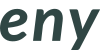材木に真っ直ぐな線を引く墨打ちという工程に、墨つぼは必須の大工道具です。古くは日本の寺社仏閣建築時にも使用されていたほどです。メーカーでは主にタジマやシンワから多くの商品が発売されています。
現代ではレーザーによる線表示が主流になったため、墨つぼの利用は減ってきましたが、商品の種類は豊富にあります。そこで今回は、あると便利な機能やおすすめの人気商品をご紹介します。是非参考にしてみてくださいね。
墨つぼの使い方

墨つぼは材木へ直線を引くために用いられる、大工道具の一種です。糸を収納しているドラムと墨タンクがある本体、カルコと呼ばれる糸付きの針によって構成されています。
墨つぼを使う時には、線を引き始めたい場所にカルコを刺して固定します。その後にゆっくり糸を引き出していきましょう。糸は墨タンク内に詰まった綿を通るので、出てくるときには墨を含んでいます。
あとは引きたい線の終端部で墨つぼを留め、伸ばした糸の中央付近を軽く上に持ち上げて弾きます。糸が材木表面へとぶつかることで墨が転写されて、真っ直ぐの線が引ける仕組みです。
直線を引くだけなら定規でも出来るのでは……と思うかもしれません。しかし、長い線となると普通の定規では手間がかかりますし、何度も定規を当てていくうちに曲がっていく可能性もあります。墨つぼは、長い直線を一度に引けて、正しく使えば曲がらないのが利点です。
墨つぼとチョークラインの違い

出典:amazon.co.jp
墨つぼとチョークラインの違いは、引かれた線が墨かチョークか、という点です。わずかな違いのようですが、使い勝手の上では意外と大きく影響してきます。
チョークラインは墨つぼと同じ用途・構造の道具で、タンクに入っているのは墨ではなく粉チョークです。そのため、引き出した糸には粉チョークが付き、墨つぼと同じように使っていけばチョークによる線が転写されます。
粉チョークなので、線がズレた場合でも簡単に消せるのがチョークラインのメリットです。墨つぼでは一度引いた線は消しづらいのですが、チョークラインであれば何度間違えても消して引き直せます。
一方、線の見えやすさでは墨つぼの方が上です。粉チョークはうっすらとした線なのに対し、墨はくっきりと視認できます。初心者や失敗の許されない作業ならチョークライン、ある程度慣れてきたら墨つぼと考えるとよいでしょう。
墨つぼの選び方
墨つぼははっきりと線付けをしたい時に最適な道具です。それだけに墨つぼ選びの際には、線をどのように引きたいのかを考えなくてはいけません。
糸を押さえる部分の形状・本体に付属している機能・糸の太さでそれぞれ考えていきます。この3つの要素は、引かれる線にどのような影響を与えるのでしょうか。
糸を押さえる部分の形状で選ぶ
昔ながらの墨つぼには、糸の出る部分に陶器製・真鍮製の部品をはめて、糸を押さえる役割をさせていました。現代の墨つぼでは、糸を押さえる部分が最初から作られています。
この糸を押さえる部分の形状により、斜めカットタイプと鶴首・バリカンタイプの2種類に分けられます。どちらのタイプかで利便性が異なるため、墨つぼを使う場所を想い描きなら選んでください。
押さえる面積が大きく安定しやすい「斜めカットタイプ」

出典:amazon.co.jp
斜めカットタイプは、墨つぼ本体の糸を出す場所が斜めに切られた形状のものです。この斜めにカットされた場所で直接押さえるので糸が安定しやすく、ピンと張りやすくなっています。
ただし、押さえる箇所が墨つぼ本体に近いため、作業場所によっては適さないケースもあります。墨つぼは結構な大きさがあり、たとえば線の終端を壁近くにしたい場合には糸を押さえるのに邪魔になってしまうでしょう。同様に狭い場所でも不適なタイプです。
狭い場所や隅でも押さえやすい「鶴首・バリカンタイプ」

出典:amazon.co.jp
鶴首・バリカンタイプは、墨つぼ本体からガイドのように伸びたパーツによって糸を押さえます。このパーツは細く伸びているため、斜めカットタイプでは適さない場所でも使用可能です。使わない時には本体に収納できる製品もあります。
一方、押さえる部位が狭くなってしまうので、糸の固定が不安定になります。斜めカットタイプで十分な場所なら、鶴首・バリカンタイプを選ぶ意味はあまりありません。
便利な機能で選ぶ
墨つぼの構造は単純ですが、より便利に使えるようにさまざまな機能を持たせた製品が売られています。糸の交換や自動巻取、墨色の使い分けができるタイプがありますから、特徴を見ていきましょう。
糸を交換できると便利

出典:amazon.co.jp
墨つぼを使っていると、糸がほつれてきたり切れたりすることがあります。糸の長さに余裕があればカルコに結び直せばよいものの、残りが短すぎると満足に線を引けません。そんな場合に便利なのが糸を交換できる機能です。
糸交換ができれば墨つぼ本体の買い替えをせずに済みますし、この機能がついていても本体価格には大して影響しません。糸交換のやり方は取扱説明書や、メーカーHPに説明・動画があるので、行う前には確認しましょう。
糸を巻き取る手間が省ける自動巻取機能付き

出典:amazon.co.jp
墨つぼで線を引いた後は、引き出した糸を回収しなくてはいけません。昔ながらの墨つぼにはドラムを回せるハンドルがついていますが、時には数mも使う糸の回収は骨が折れます。糸回収を手軽に行えるのが自動巻取タイプの墨つぼです。
自動巻取機能は内部にゼンマイを内蔵していて、ボタン1つで自動的に巻き取る仕組みです。ただ、機種によって自動巻取できる長さは決まっています。自動巻取タイプを考えているのなら、よく使う長さをカバーできるように選んでください。
黒と朱で色を使い分けたい人におすすめの二色タイプ

出典:amazon.co.jp
墨つぼでの線引きは黒い墨汁が基本ですが、中には朱液入りタンクもついている二色タイプもあります。墨汁の黒さを残したくない化粧材に線を引く場合、朱液であれば目立ちません。
使う墨液が二種類になるため、本体重量やサイズが大きくなる傾向が見られます。また、二色といっても黒い墨汁のタンク容量を大きく取っているため、朱液はおまけと考えた方がよいでしょう。
糸の太さで選ぶ
墨つぼは糸に墨を含ませて線を引く工具ですから、使う糸の太さによって引ける線の太さも変わります。代表的なのは1mm・0.6mm・0.4mmの3種です。
はっきりとした線を書きたいなら「1mm」

出典:amazon.co.jp
1mmの糸はかなり太さがあり、はっきりとした線を出せます。線の切れを起こしたくない、表面に色や模様があって細い線は見えづらいケースで役立つでしょう。
ただし、1mmの糸は基本的にチョークライン用です。墨つぼで使うと太さがあるだけに墨をよく吸うので、墨汁の消費が早くなります。
太さを気にしないのであれば「0.6mm」

出典:amazon.co.jp
糸の太さでおよそ中央付近に当たるのが、0.6mmタイプです。一般的な糸から耐久性を高めた糸まで、幅広い種類が見られます。
0.6mmの糸は目立った欠点がないため、採用している商品が多い傾向です。糸のタイプで迷ったなら0.6mmを基準に考えてみてください。
細い線を書きたいなら「0.4mm」

出典:amazon.co.jp
0.4mmの糸は一般的に使われる中でもっとも細いタイプです。繊細な線を引けるので、材木に汚れを残したくない作業に好んで用いられます。
一方で、0.4mmの糸では線が細いために見えづらいケースが出てきます。糸の細さは墨の乾きやすさにも繋がるため、墨つぼの扱いに慣れた人向きです。また、墨つぼの糸は摩耗しやすいので、0.4mmは使っている最中に切れる可能性もあります。0.4mmを使うなら強化されている糸を選びましょう。
墨つぼのおすすめ人気ランキング7選
以上のように、墨つぼを選ぶ時に見るのは本体の形状・付属機能・糸の太さであることが分かりました。それでは以下で、おすすめの商品7個をランキング形式でご紹介していきます。
1位 シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 73282

amazon.co.jp
155 g:155 g
0.6 mm:0.6 mm
15 m:15 m
自動巻取(8 m):自動巻取(8 m)
斜めカット・鶴首どちらにも使える便利な墨つぼ
シンワ測定が送る、安価でありながら十分な機能を持っている墨つぼです。糸の押さえは基本的に斜めカットタイプですが、ワンタッチ操作で糸ガイドを引き出すことで鶴首にもなり、隅の方への墨打ちも簡単です。
内部の墨タンクはゴムパッキンによる密閉型で、墨漏れを起こしにくい構造です。墨が少なくなってきたらドラムの下にある墨付けボタンを押せば、内部でスポンジが絞られて濃く鮮やかな色を出せます。
墨つぼ本体はコンパクトで、上部にはフック穴がついています。この穴にナスカンを引っかけて工具ベルトに固定できますから、高所作業でも落としてしまう心配がありません。一般的な室内作業から平場まで、いろいろな場所の墨打ちに活躍してくれるでしょう。
2位 タジマ パーフェクト墨つぼ PS-EVO-M

amazon.co.jp
重量:167 g:重量:167 g
糸の太さ:0.6 mm:糸の太さ:0.6 mm
糸の長さ:20 m:糸の長さ:20 m
機能:自動巻取(10 m):機能:自動巻取(10 m)
墨の扱いを重視したタジマ製
工具なしでも全開できて、メンテナンスや糸交換しやすいフルオープン構造の墨つぼです。特徴的なのは内部の構造で、墨を無駄にしないように考えられています。
内部のつぼ綿はセルロースのスポンジで墨含みがよく、糸にしっかりと墨をつけられます。スポンジ形状はH形で糸の出口にまで繋がっていません。さらに一体型ゴムパッキンで守られているので、墨汁の漏れ・乾燥を防いでくれる親切設計です。
自動巻取だと糸が勢いよく戻って針先で怪我するおそれもありますが、この製品では針が自動的に収納されるポイントカルコを採用しています。墨漏れ防止や安全性から墨つぼを選びたい方にピッタリです。
3位 タジマ パーフェクト墨つぼ GUN PS-SUM6GNX

amazon.co.jp
重量:124 g
糸の太さ:0.6 mm
糸の長さ:15 m
機能:自動巻取(6 m)
使いやすさにこだわったプロ用墨つぼ
この墨つぼは見た目に美しいだけでなく、内部にもこだわっています。まず、持ち手となるリール付近にはゴムグリッドを採用。糸を押さえている最中に手が滑りにくく、線のブレ・ズレを防いでくれます。
糸を押さえる部分はやや裾広がりになっています。この形状は斜めカット・鶴首のよい所どりをしたマルチヘッドで、平面でも隅でも糸を押さえやすくなり、用途が広がりました。
本体はフルオープンできる構造です。墨の補充・綿の交換・汚れの掃除・糸交換が簡単に行えます。定期的にメンテナンスすれば長く使えますから、何度も墨打ちするプロの方にもおすすめです。
4位 シンワ測定 ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 73287

amazon.co.jp
重量:190 g
糸の太さ:0.6 mm
糸の長さ:20 m
機能:自動巻取(10 m)
耐久性抜群の糸で長く使っていける
多くの測定器具を販売しているシンワ測定の墨つぼです。糸を押さえる部分は斜めカットで、広い面積で押さえられるので線のズレが起きにくくなっています。
付属の糸が「タフライン」と銘打っているように強靭で、従来より1.2倍の回数の墨打ちができるとのことです。糸の長さも20mとたっぷり余裕があるので、1つ買えば長く使えます。ホルダー対応モデルなので、シンワ製のホルダーも一緒に購入を検討してはいかがでしょうか。
5位 タジマ パーフェクト 楽つぼB PS-RAKB

amazon.co.jp
重量:235 g
糸の太さ:0.6 mm
糸の長さ:20 m
機能:自動巻取(10 m)
機能豊富で使い込むほどに魅力が増す
やや大型の墨つぼで、墨タンクの容量がなんと60mlもあります。7~15mlが一般的な墨つぼの中では破格の容量です。
自動巻取では徐々に減速する自動減速機能、糸切れ時の逆転防止機能がついているので、安全に使えるのではないでしょうか。本体がやや複雑ですが、慣れればとても使いやすくなります。
6位 タジマ(Tajima) パーフェクト墨つぼ ボム PS-SUM6BMHI

amazon.co.jp
重量:116 g
糸の太さ:0.4 mm
糸の長さ:15 m
機能:自動巻取(6 m)
細い糸で繊細な墨打ちをこなせる
タジマ製の墨つぼで、0.4mmと細い糸は造作材への墨打ちにピッタリです。カルコ針の収納付きなのでケガの心配も軽減できます。墨の容量が7mlと少なめな点は不安要素でしょう。
7位 たくみ 自動巻すみつぼ PIT

amazon.co.jp
重量:190 g
糸の太さ:0.6 mm
糸の長さ:11 m
機能:自動巻取(5.5 m)
小型で扱いやすい墨つぼ
小型で取り回しやすさが魅力の墨つぼです。本体はフルオープンできる構造なので、糸交換が難しくありません。ただ糸の長さは短めなので、そこは注意してください。
おすすめの商品一覧
| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |
|---|---|---|---|

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plu……
1
|
1,179円 |
     4.4 |
    |

タジマ パーフェクト墨つぼ PS-EVO-M
2
|
1,589円 |
     3.85 |
    |

タジマ パーフェクト墨つぼ GUN PS……
3
|
1,939円 |
     4.25 |
    |

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Pro Pl……
4
|
2,152円 |
     4.4 |
    |

タジマ パーフェクト 楽つぼB PS-R……
5
|
2,497円 |
     4.25 |
    |

タジマ(Tajima) パーフェクト墨つ……
6
|
1,786円 |
|
    |

たくみ 自動巻すみつぼ PIT
7
|
1,193円 |
    
|
    |
あったら便利なおすすめ関連商品
墨つぼは販売されているものをそのまま使えるようになっています。墨を含ませた糸を打ち付けるだけなので簡単そうですが、作業場所や使用者の技量によって、一般的な墨つぼでは適さないことも少なくありません。
以下で、墨つぼに使える便利な商品をご紹介します。あれば便利なアイテムですから、使用環境にあわせて使ってみてください。
鉄板など金属に墨打ちする際に便利なマグネット付きカルコ

出典:amazon.co.jp
墨つぼはカルコを針で固定して線の始点にしますが、金属には針が通りません。鉄板への墨打ちをするならマグネット付きのカルコが便利です。磁力によって固定してくれるので、鉄板でも楽に直線を引けます。
鉄板上で動かないよう固定するため、マグネットは強力でなくてはいけません。しかし、作業中にはネジ・ドライバー・ドリルなど金属工具が多いため、マグネットが他のものを引っ付けないように注意が必要です。
失敗しても安心の消える墨汁

出典:amazon.co.jp
墨汁で線を引くと、位置を間違えたり失敗したりといった場合でもやり直しはできません。墨つぼが難しいのはこの点ですが、消える墨汁を使えば万が一の失敗でもやり直せます。
消える墨汁の中身はアルカリ性の液体です。使った直後は線が見えますが、中和されて中性になると見えなくなります。墨つぼの扱いにまだ慣れていない場合に使ってみるとよいでしょう。
消える墨汁は、未使用の墨つぼに使用しましょう。使用済みのものでは、普通の墨と混ざってしまい、消える特性を発揮できません。また、墨打ちする対象が酸性・アルカリ性のどちらかで線の消える速度も変わるので、使用前に注意書きをよく読んでください。
まとめ
墨つぼは古くから存在している大工道具です。基本的な構造は昔から変わっていませんが、より使いやすいようにさまざまな機能をつけた製品が販売されるようになりました。
機能面では糸を押さえる部分の形状や本体の機構などの違いが見られます。糸の太さによっても使用感が変わるので、選ぶ際には特徴をよく把握しておきましょう。